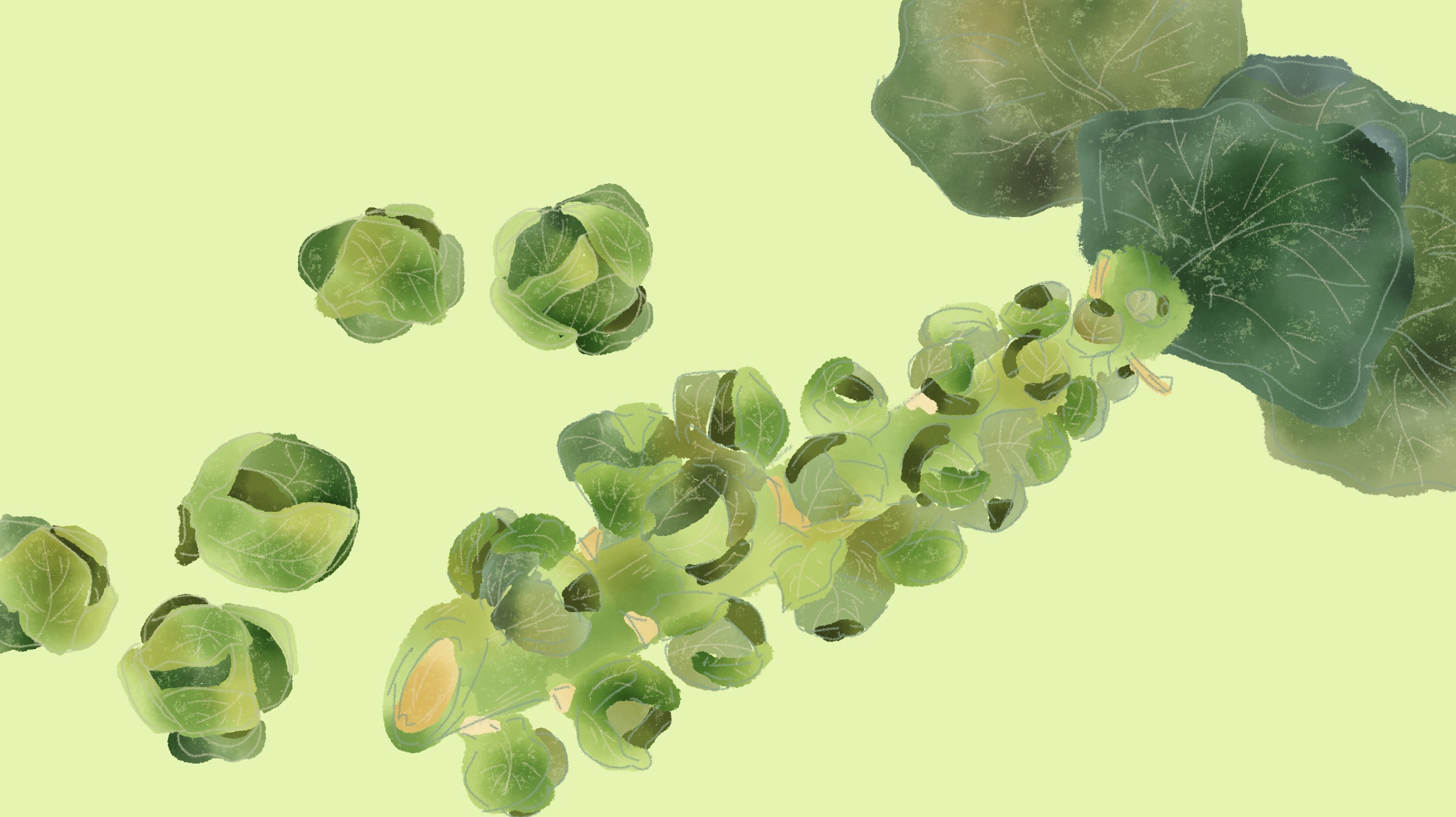自然のいろは|正藍冷染「灰汁とり」

季節や植物によって“ゆらぎ”のある「色」、経年変化していく“移ろい”のある「色」
そんな「自然の色」を使ったモノづくりには、
草木から色を作り出す一手間、何度も重ねて染色する一手間。
決して楽ではない工程を、あえて選択するのはなぜでしょうか?
そんな“ままならない”、「自然の色」に心惹かれている方々へ話しをお聞きしていきます。
今回は、日本最古の染色技術といわれる『正藍冷染』をされている
4代目・千葉正一さんの元へ伺い、「灰汁とり」の様子を見せていただきました。
「正藍冷染は、灰汁が大事。良い灰汁がとれないと、藍は染められないんです」千葉さんにお会いしてから、藍染のことを聞く度に話題に上がる“灰汁(アク)”。この作業は、1日、2日で終わる作業ではなく、来年の夏に藍を染めるのに必要な灰汁がとれるまで行われます。その期間は、およそ11月から12月末まで。今年も毎日、この灰汁とりの作業が行われています。
取材に訪れたのは、11月末。藍染の作業の中でも重要なこの『灰汁とり』の作業を見せていただきました。

「ちょうど、今が撮影するのに良いタイミングだよ」そう言って、作業場へ案内してくださいました。その先では、コンコンと燃える薪。外からの土や汚れを持ち込まないように、靴を履き替え、そっと部屋に入ります。
「藍は生き物。汚いものを嫌うんですよ」と千葉さん。自然に声も小さく、神妙な気持ちになります。

「そもそも“灰汁(アク)”とは?」とお思いの方もいらっしゃいますよね。灰汁は藍染などの染め物でよく用いられます。一般的な染め物では、草木の灰(藁や木の炭)を水に浸して、上澄み液のみを使います。一方、千葉さんの受け継ぐ「正藍冷染」では、楢(なら)の薪を燃やして固まった灰を一度粉々にし、そのまま灰汁として使用します。
「ただ薪を燃やせばいい訳ではないのです。そんな簡単じゃないんです。先代に教えてもらってから、自分で藍を染めてみても、全然染まりませんでした。どの作業も同じようにしているのに、です。なんでだろう、と。最初の3年くらいは分からなかった。そして、この灰汁の出来が関係しているのでは、と気が付いてから、やっと藍の色が出るようになりました」


「灰汁と聞くと、サラサラとした細かい灰を思い浮かべる人が多いと思います。うちでは、このように固まった灰が良い灰汁になります。毎朝6時に火をつけ、午後4時まで薪を継ぎ足します。午後4時以降は、そのままいじらずにそっとしておく。そうすると翌朝にはこのように固まるのです」
ブリキのバケツから取り出し、見せてくれたのは固まった灰。大きいもので、片手からはみ出すほどのサイズ。灰がこんな風に固まるなんて、見せてもらうまで知りませんでした。
「固まっても、割った時に中まで黒いものが良い。今年も11月から燃やし始めて、最初の10日間くらいは良い灰が全くとれませんでした。できた灰も使えない。ただ薪を無駄にしただけになってしまいました。
ですが、ここ数日でやっと安定してきました。この調子でとれれば、今年の年末までには終わりそうです」

「こうやって、良い灰がとれても藍が染まるとは限りません。来年、染めてみるまで分からないんです」集めた灰は来年の『藍立て』の5月まで保管されます。毎日薪を燃やし続けても、上手くいくとは限らない。藍もまた生き物。自然や生き物の前では、なんでも人間の都合の良いように進まないのですね。

「毎日燃やすので、相当な薪が必要になります。その薪もここ数年、値上がりしていてね。楢(なら)の薪じゃなきゃ、絶対ダメなんですよ。
楢の薪を使う家もこの辺は減ってしまって、恐らく宮城県だとうちくらいしか使っていないんじゃないんですかね。つくっているのも秋田県か山形県の方。森林組合の人に届けてもらっています。うちが薪を使うのを知っているからね。ただ、楢の木も減っているからいつまで薪が手に入るか分からない。薪がなくなったら、正藍冷染も出来なくなってしまうだろうね」

調べてみると、近年、全国的に“ナラ枯れ”が発生し、樹木が大量に枯れてしまう被害が増えているとのこと。“ナラ枯れ”とは、カシノナガキクイムという虫が木にもぐりこみ、虫の持つナラ菌が樹木に感染し引き起こす、木の伝染病だそうです。
さらに、薪を使う人も減ったので、木を薪にする人も減少。結果、薪の値段も上がっています。千葉さんは伝統と技術を守るべく「正藍冷染」を続けていらっしゃいます。ですが、続けられなくなってしまう原因が、薪や森林問題、さまざまな問題が複合的に関係していることを知りました。
『共生をいうなら、共死を覚悟せよ』最近読んだ本の中で出てきた言葉です。農家さんをはじめ、自然を扱う人たちの言葉、生き方にはある種の覚悟を感じるのです。
プロフィール
正藍冷染(しょうあいひやぞめ)|4代目・千葉正一さん
宮城県栗原市の千葉家に代々伝わる『正藍冷染(しょうあいひやぞめ)』。その特徴は、自然の温度で発酵させること。藍の栽培から自然発酵、染めまでを一貫して行う『正藍冷染』は、日本最古の染色技術とされています。
昭和30年には、『正藍冷染』が貴重な技術であることが認められ、初代・千葉あやのさんが国の重要無形文化財技術保持者(人間国宝)に指定されました。その後も2代目・千葉よしのさん、3代目・千葉まつ江さん、そして4代目・千葉正一さんへと受け継がれています。他の地域では絶えてしまった技術を守り、後世にも残すべく千葉家が継承し、今に至ります。